|
速記講座【18】 長イ音
−−−−−−−−−−−−−−−−− 長イ音は線を流します。「ながい」は「ながす」と覚えてください。 さあ、どういう書き方でしょう。 書道では、「永字八法(えいじはちほう)」といって、「永」の字の書法には、 漢字の楷書に必要な8種の技法がすべて含まれているそうです。これがすべての 漢字の書き方の基礎になっているそうです。 「永」という字の筆順のまま、 (1) 側(ソク……点) (2) 勒(ロク……横画) (3) 努(ド……縦画) (4) 趯(テキ……はね) (5) 策(サク……右上がりの横画) (6) 掠(リャク……左はらい) (7) 啄(タク……短い左はらい) (8) 磔(タク……右はらい) というふうになっています。 さて、速記文字ではどうでしょう。速記文字というのは単純な線のつながりか らできていますから、「永字八法」ほどの複雑なことはやっておれません。 普通に書いて終わりをとめるのを「とめ」とすれば、書き終わるときに軽く力 を抜いたのが「流し」でしょうか。その2つの書き方ぐらいです。ここで言う 「流し」は、「永字八法」で言うなら「はらい」に近いでしょうか。 ただ、速記の場合は1字ずつ独立せずに言葉単位で続けますから、次の線を書 くときにそのまま続けていくか、紙面から離筆して線と線とのつなぎ目にほんの 少し空間を入れるかの違いになります。 言葉で説明すると難しく感じますね。図で確かめると一目瞭然ですよ。 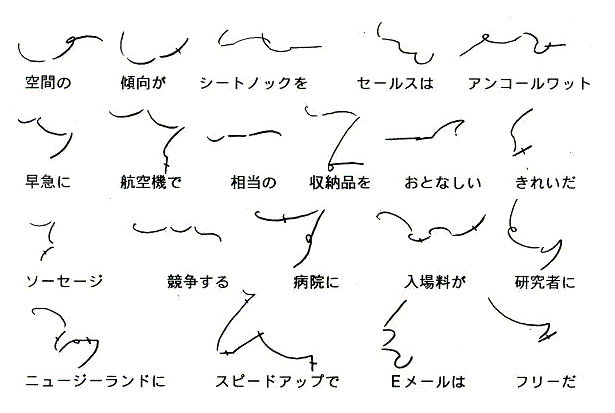
線尾を流すことによって次の字との間に小さな空白をつくるということですね。 でも、単群(速記文字の一固まり)の最後に出てきた場合は区別がつくでしょう か。 鉛筆で書いたものならはっきりとわかります。その他の筆記具で、もしわかりに くい場合があれば、次の線の代用品として、線尾を流した延長上に点をつけると はっきりするでしょう。 −−−−−−−−−−−−−− ところで、「永字八法」といえば、昔の中国東晋の書家「王 羲之」という人 は、何と15年間にわたって「永」の字を練習して八法の原理を体得し、それによ ってすばらしい書をつくり出していったと伝えられます。 そして、古今の書家をはじめ書を愛する多くの人たちに、歴史上最初に書を芸 術の域に高めた天才そして書聖として仰がれているそうです。 なお、「永字八法」の「(4) 趯(テキ)」の字は、扁(へん)の「走(そうに ょう)」に「曜」や「躍」の右側の旁(つくり)を組み合わせたものです。 −−−−−−−−−−−−−−−−− きょう覚えること……「ながい」は「ながす」だけです。(念のため) |
